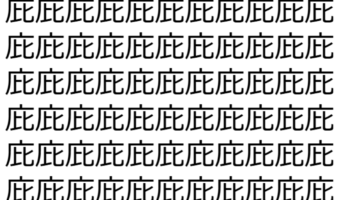おでんや揚げ物、納豆などに用いられる「からし」。
このからしは「からし菜」の種子を用いて作り、和からしともいわれます。
似ていますが別物として、洋からしやマスタードがありますが、原料や作り方が異なります。
そこでここでは、「からし」の原料についてや、洋からしやマスタードの原料や作り方の違いについて見ていきましょう。
目次
「からし」の材料と作り方

まずは「からし」の材料と作り方を見ていきましょう。
「からし」の原料は「からし菜」の種子
からしの原料は、「からし菜」という植物の種子です。
からし菜はアブラナ科アブラナ属の植物で、チンゲン菜や白菜の仲間となります。
そんなからし菜は、中央アジアが原産とされています。
地中海沿岸から伝播する間に交雑によって生まれたとされています。
日本に伝来したのはかなり古く、弥生時代に伝わったと考えられています。
現在では、野生種などが川沿いの土手などに生えています。
栽培種の場合は、10月~12月に種を蒔いて育てられます。
最盛期は花が咲く前の春先で、2月~3月が旬となります。
からし菜自体としては、葉茎を油炒めやお浸し、漬物などに利用されます。
「からし」の作り方
スタンダードなからしの作り方は以下の通りなのですが、非常にシンプルです。
まず、からし菜の種子をすりつぶします。
すりつぶし、粉末にしたものをぬるま湯などで溶いて練り上げます。
こうすることろで「和からし」とも呼ばれる、からしが出来上がります。
「洋からし」との違い

にほんでは、からしと言えば一般的に和からしのことを指します。
しかし、食卓には「洋からし」と呼ばれるものが並ぶことがあります。
ここからはそんな洋からしとの違いを見ていきましょう。
「洋からし」の材料
洋からしの材料は、シロガラシの種子と酢と砂糖となります。
つまり、和からしとは原料からして違ってくるわけです。
ちなみにシロカラシは欧米が原産とされています。
そのため、欧米で広く使われる調味料となります。
「洋からし」の作り方
洋からしの作り方は和からしとほぼ同じなのですが、調味料を加えるという違いがあります。
まず、シロガラシの種子をすりつぶします。
粉末になったものを、ぬるま湯と酢やワインビネガー、場合によっては砂糖を加えて練り上げます。
洋からしの場合は、酸味や甘味を加えることがあるという事になります。
「マスタード」との違い

からしの中には「マスタード」と呼ばれるものもあります。
しかし、このマスタードは洋からしと同じものです。
その名前は「ムスツム・アルデンス(燃えさかる新ぶどう酒)」というラテン語が由来だそうです。
「マスタード」の材料
マスタードは、洋からしの英名です。
ホットドッグなどにケチャップなどとともにかけるソース状のマスタードは、アメリカ生まれの調味料で「イエローマスタード」や「アメリカンマスタード」とも呼ばれます。
また、マスタードと呼ばれるものに日本でもおなじみの「粒マスタード」もありますが、こちらはフランス生まれとなっています。
「粒マスタード」の作り方
フランス生まれの粒マスタード、からしや洋からしと違い粒が残っています。
しかし、作り方は両者に近しいです。
からしや洋からしの場合、種子を粉状になるまですりつぶしますが、粒マスタードの場合は種子の形が残っている程度につぶす程度に抑えます。
この荒くつぶした種子をワインビネガーや酢に漬け込んだら完成です。
酢やワインビネガーに漬け込んでからつぶす、という手順でも大丈夫です。
まとめ
からしと洋からしの違いは大きく分けて2つ。
ひとつは原料となる植物の違い、もう一つは練る際に酢やワインビネガーもしくは砂糖といった調味料を加えるか否かです。
からしはマスタードと呼ばれる事もありますが、これは洋からしの英名になります。
とはいえ、マスタードと一口に言っても種類は豊富です。
たとえばホットドッグなどにかけるものはアメリカ生まれの「イエローマスタード」や「アメリカンマスタード」、種子の形状が残っているものはフランス生まれの「粒マスタード」で、味わいも形も異なります。