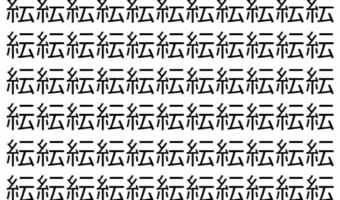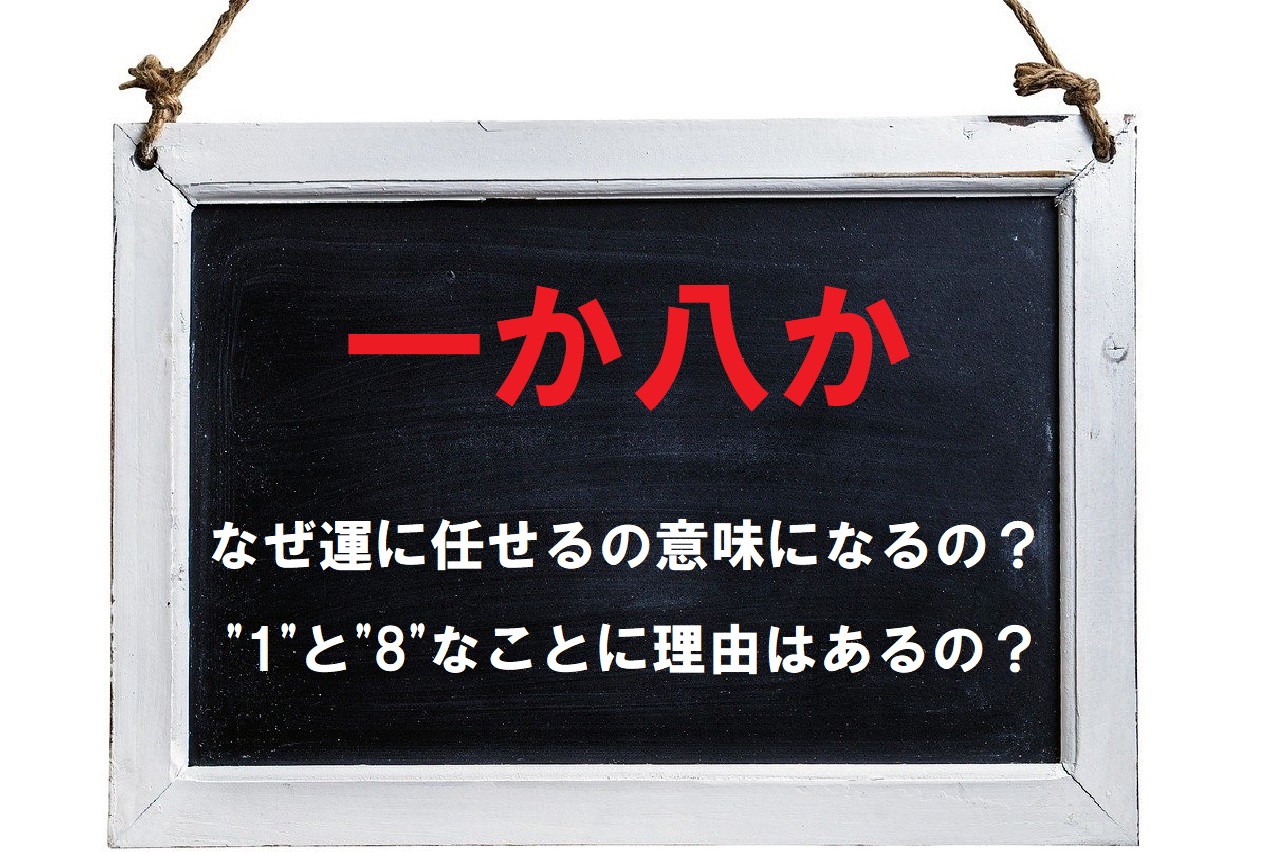
運に任せて賭けることを「一か八か」と表現することがあります。
この「一か八か」は、ギャンブルの世界などで多用される表現です。
また、仕事やテスト、試験の場においても「あとは一か八かだ」と後は運に任せる際に使用されます。
ではこの言葉、なぜ「1」と「8」なのでしょうか?
そこでここでは、この「一か八か」という言葉について意味やその成り立ちとなる由来を見ていきましょう。
目次
「一か八か」とは

まずは「一か八か」が、どのような状態をあらわすのかを見ていきましょう。
「一か八か」の意味
「一か八か」は、結果はどうなろうと運を天に任せてやってみることを意味する表現です。
後の無い一本勝負などにおける意気込みを指す表現となります。
運をすべて天に任せてしまうことを指す言葉です。
主に、これから行う事の結果がわからない際に対して使うことが多いです。
対義語は「慎重さをあらわす言葉」
「一か八か」の対義語は、慎重さをあらわす言葉が当てはまります。
例えば「堅実」や「石橋を叩いて渡る」などがそれに該当します。
ここからは「一か八か」の対義語を見ていきましょう。
堅実
「堅実」とは、手堅く確実なことを指した表現です。
しっかりしていて危なげない手段や行動をあらわします。
運任せの「一か八か」と比べると正反対の考えによる行動や思考となります。
石橋を叩いて渡る
「石橋を叩いて渡る」は、たとえそれが堅固な石橋であっても安全を確かめてから渡ることからきた言葉です。
これが転じて、用心した上でさらに用心深く物事を行うことの例えとして使用されます。
「一か八か」の由来

では、そもそもなぜ「一か八か」なのでしょうか?
「二か四か」ではダメだったのでしょうか?
ここでは1と8になった理由について見ていきましょう。
賭け事のひとつ「丁半賭博」から来たとする説
「一か八か」は、「丁半賭博」というサイコロを用いたギャンブルが由来とする説があります。
これはサイコロを2つ振り、偶数の「丁」、奇数である「半」どちらが出るかを当てるというものです。
「一か八か」は、この丁半博打のこと自体から来ているとされます。
丁の上部にある「一」と、半の上部にある「八」、このふたつを取って「一か八か」と表現するようになったとされています。
これが、次第に運任せの勝負に対する意気込みという意味で使われるようになったわけです。
もともと「一か罰か」だったとする説
博打用語には、「一か罰か」という言葉もあります。
これが「一か八か」の由来とする説もあります。
「一か罰か」は、サイコロの目が「一が出るかしくじるか」を指した言葉です。
この「一か罰か」が転訛したことで、「一か八か」となったともされています。
「一か八か」の類義語

ここからは「一か八か」の類義語を見ていきましょう。
類義語としては、「伸るか反るか」「乾坤一擲」「清水の舞台から飛び降りる」などがあげられます。
伸るか反るか
「伸るか反るか」は、成功するか失敗するかわからないものの、運任せで思いきってやってみるという意気込みをあらわす言葉です。
確実に成功する場合も、失敗が確定している場合も「伸るか反るか」とは表現することがありません。
あくまで結果がわからないことに対して、運任せで行動する際に用いられます。
乾坤一擲
「乾坤一擲」とは、運命を賭けて一世一代の勝負をすることをあらわす言葉です。
これは前漢の初代皇帝となる劉邦が、項羽に対して戦いを仕掛けるようにと家臣から進言を受けて出陣したという故事に由来するとされています。
「乾」は天を、「坤」は地をあらわしており、「一擲」は一度投げることや全てを投げ出しを指します。
勝てるかどうかは分からない相手に対し全てをかけて戦いに挑んだその様子から、一世一代の大勝負をあらわす言葉として使用されるようになりました。
清水の舞台から飛び降りる
「清水の舞台から飛び降りる」とは、思い切った決断をすることです。
清水寺の本堂から飛び降りるくらいの覚悟を示した言葉となります。
明治時代までは、実際に飛び降りた人が相当数いたそうですよ・・・。
まとめ
「一か八か」は、運を天に任せて行動することをあらわす言葉です。
この言葉は、博打に由来があるとされています。
「丁半博打」や「一か罰か」から来たとする説などがあります。
関連記事はこちら
「はったり」の語源は賭博にあった?!その由来を意味と併せてご紹介!