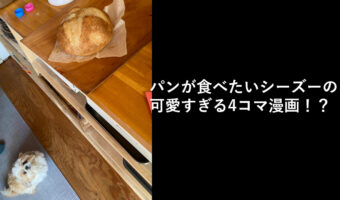極めて僅かな期間や非常に短い時間のことを「一朝一夕」と表現することがあります。
この言葉は、朝から夕までの1日を指しています。
ここでは、この「一朝一夕」という言葉について、その意味や用い方、類義語に対義語について見ていきましょう。
目次
「一朝一夕」とは

まずは「一朝一夕」という言葉について見ていきましょう。
「一朝一夕」の意味
「一朝一夕」とは極めて僅かな期間、非常に短い時間の例えた言葉です。
朝の間と一晩の意から来ています。
「1日かそのくらいの時間」と、1日を僅かな期間とするニュアンスで用いる言葉となっています。
「一朝一夕」の用い方・例文
「一朝一夕」は、「一朝一夕では○○できない」などのように打ち消し表現を伴うことが多いです。
例えば「一朝一夕では、弁護士試験に合格できない」など、否定で使用されることがほとんどです。
簡単ではない、難しいといった意味合いで使われます。
そのため、「一朝一夕で資格を取得できた」など肯定で用いることはほとんどありません。
何かを達成したことに対して賛辞を送る際には、「それは一朝一夕でできることではないよ」という表現をすることができます。
「一朝一夕」の由来

では「一朝一夕」はどのようにして成立した言葉なのかを見ていきましょう。
由来は中国の古典の一節から
「一朝一夕」は、中国の古典「易経」の一節から来た言葉とされています。
その中に、「臣其の君を弑し、子其の父を弑するは、一朝一夕の故に非ず」と一節があります。
これは「君主に手をかけたり、子が親を殺めるという事態は突発的な行動ではなく、長い年月の積み重ねによって起こるものだ」という意味です。
そこから「予兆があれば早期に対策を講じるべきである」という教訓として使用されてきた言葉です。
この言葉が、「何事も短期間ではできない」という意味にも転じたのが、今日の「一朝一夕」の由来とされています。
出典の「易経」とは
「易経」とは、古代中国にまとめられた書物です。
殷や商と呼ばれる時代から蓄積された卜辞の集大成として成立したものです。
陰と陽という二大要素が対立したりまとまることで、この世界の全てに変化を生じさせるという変化法則を説く書となっています。
その著者は、神話に登場する伏羲という伝説の神、もしくは王とされる人物です。
「一朝一夕」の類義語と対義語

最後に「一朝一夕」の類義語と対義語を見てみましょう。
類義語は「一寸光陰」
「一朝一夕」の類義語としては、「一寸光陰」があげられます。
「一寸光陰」とは、極めて僅かな時間のことを意味します。
古くは少ない時間も無駄にしてはいけないという戒めとして使用された言葉でもあります。
「一寸」は、長さの単位であり、わずかばかりの物事を指す際にも用いられます。
「光陰」は、光と影ではなく、ここでは昼夜といった時間や年月の意味しています。
「一寸の光陰軽んずべからず」という慣用句として使用されることも多いです。
対義語は「ローマは一日にして成らず」
「一朝一夕」の対義語としては、「ローマは一日にして成らず」があげられます。
「ローマは一日にして成らず」とは、大事業は長い間の努力なしには完成されないという例えです。
ローマ帝国という大国も、1日で成立したわけではありません。
国として成立するまでも紆余曲折ありましたし、そこから日々の積み重ねがあったことで歴史に名を残す大帝国となったのです。
転じて、どのような立派なものも長年の積み重ねがあって初めて出来上がる、ということを説明する表現として使用されるようになりました。
ちなみに「一朝一夕」は否定的な表現で使われることが多いため、表現によっては類義語となる可能性もあります。
まとめ
「一朝一夕」は、僅かな期間や短い時間を指す表現です。
多くの場合は「一朝一夕では達成できない」など、否定のニュアンスを込めて使用されます。
その類義語としては「一寸光陰」が、対義語には「ローマは一日にして成らず」などがあげられます。