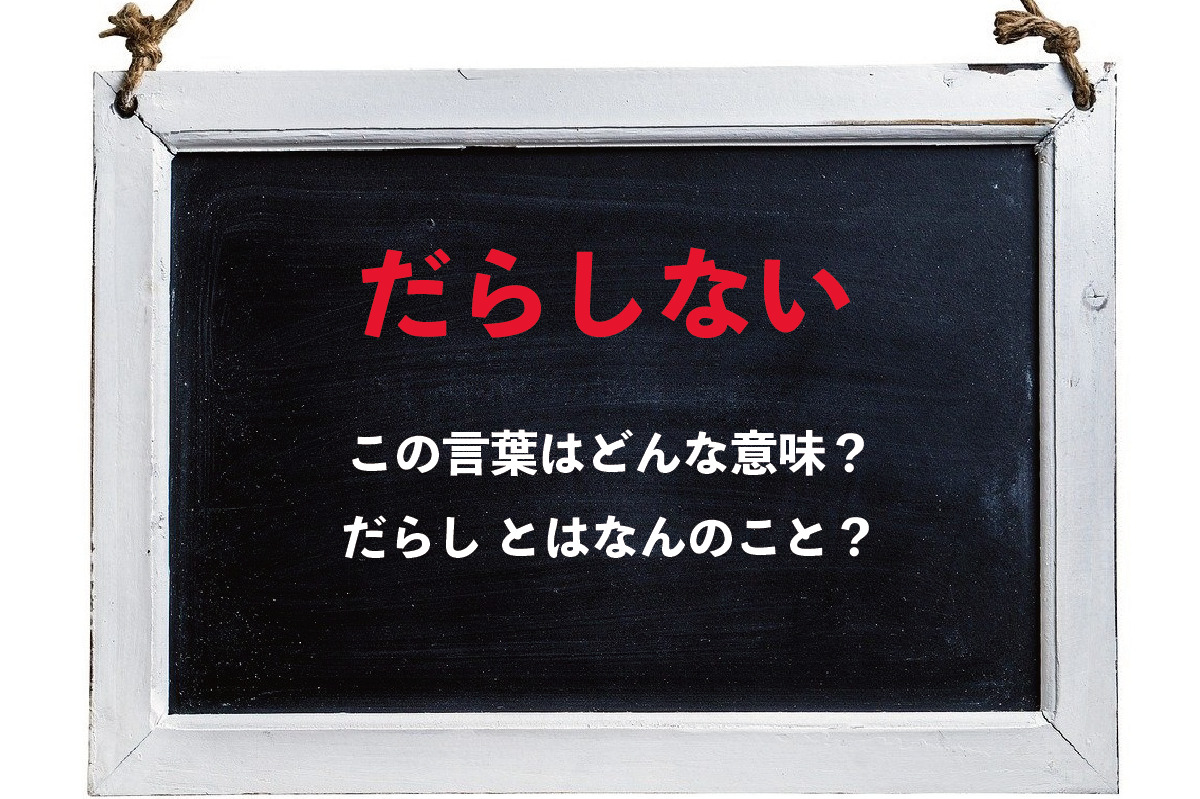
きちんとしていないことを表す言葉のひとつに「だらしない」があります。
この言葉は、整っていない状態なども指します。
性格、生活態度なども含めて咎める際に用いられます。
では、この「だらしない」の「だらし」とは何なのでしょうか。
ここでは、「だらしない」という言葉について、意味や由来、その類義語について見ていきましょう。
目次
「だらしない」とは

まずは「だらしない」という言葉について見てみましょう。
「だらしない」の意味
「だらしない」とは、きちんとしていないことや整っていないことを指す言葉です。
人物や物事に対してけじめがつかないことを指しますが、節度がないことやしまりがないことも表します。
その他、体力や気力が欠けていること、根性がないことも意味する言葉です。
「だらしない」人とはこんな人
「だらしない」は、外見と性格の両方に使用される表現です。
外見については、髪型が乱れていたり、服装が乱れていることを指します。
身だしなみや身なりが整っていない人に対して使用される表現となります。
内面については、遅刻が多かったり、約束を守らない傾向にある人に用いられます。
テキパキとできずに、ダラダラとしている人に対して使用されることの多い表現となっています。
基本的にポジティブなニュアンスで使用されることはなく、ネガティブな意味合いとなっています。
「だらしない」の由来

では「だらしない」はどのようにして生まれた言葉なのでしょうか。
もともとは「しだら」だった?
「だらしない」は、「しだら」という言葉が音転した言葉だと考えられています。
そしてこの「しだら」は「しだらない」という言葉だったのだとか。
由来とされる「しだら」とは
「しだらない」は秩序から外れているといった状態を指していた言葉です。
それが次第に「しだら」として略されて広まったと考えられています。
この「しだら」がさらに「だらし」へと変化し、更に否定形の「ない」がついたことで「だらしない」になったとされています。
「しだらない」が「しだら」に略され、「だらし」に変化した上で「ない」が付け加えられ「だらしない」になったという経路をたどっています。
「しだらない」から「だらしない」に変化したわけではない、というのがポイントですね!
「自堕落」から来たとする説
「だらしない」は、「自堕落」から来たという説もあります。
「自堕落」とは行動や態度、言動など身持ちに締まりがないことを指す言葉です。
この「自堕落」が変化して「だらしない」になったとされています。
「しどろ」が変化したという説も
「だらしない」は、擬態語の「しどろ」から変化したという説もあります。
「しどろ」とは、秩序が失われている状態を指す言葉です。
「しどろもどろ」という表現としても使用されることがある言葉です。
このしどろもどろは、「しどろ」と「もどろ」どちらも乱れていることを指します。
秩序がないことをあらわす「しどろ」が変化したことで「だらしない」が生まれたという説もあるのです。
「だらしない」の類義語

最後に「だらしない」の類義語を見ていきましょう。
類義語としては「ぐうたら」 や「ちゃらんぽらん」「ずぼら」などがあげられます。
ぐうたら
「ぐうたら」とは、気力がなくぐずぐずしている様子のことです。
すぐ怠けようとすることや不精でいい加減なことも表します。
働かないことに対して皮肉を込めて言うこともあります。
ぐうたらの「ぐう」は「愚(ぐ)」の長音化したもの、「たら」は「弛む(たるむ)」などのもとである「たる」が変化したものとされています。
ちゃらんぽらん
「ちゃらんぽらん」とは、しっかりした考えがなく、その場限りであることです。
いい加減で無責任なことを指すこともあります。
特に言動などが適当な人物や物事に対して使用されます。
ずぼら
「ずぼら」とは、行うべきことや守るべきことをしないことを意味します。
発言や行動、態度に締まりがないことを指します。
この言葉は、つるつるしたものやのっぺりしたものを表す言葉から来ているのだとか。
近世の上方の方言である「ずんべらぼん」「ずんぼらぼん」「ずんぼらぼん」などから来ているとされています。
まとめ
「だらしない」は、身だしなみや性格に締まりがないことを言います。
これらは「しだらない」という似たような意味を持つ言葉から生まれた言葉と考えられています。
類義語としては「ぐうたら」 や「ちゃらんぽらん」「ずぼら」などがあげられます。




