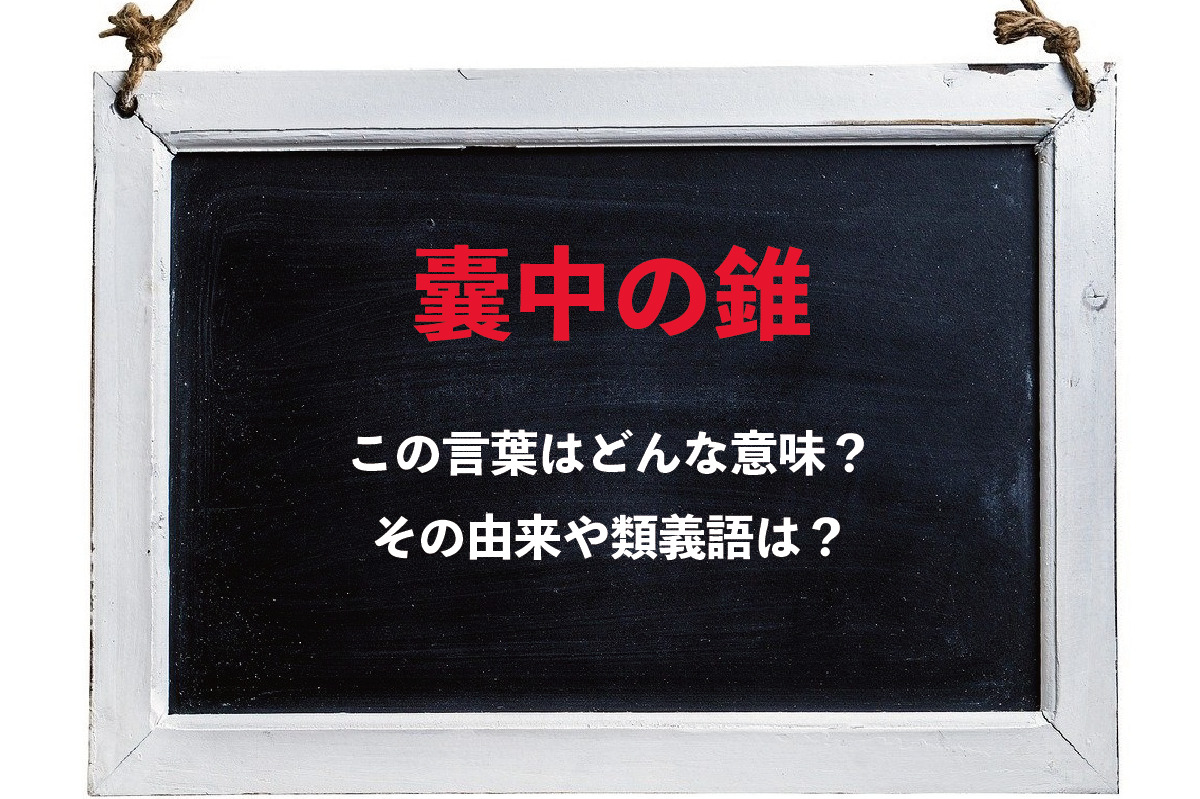
優秀な人は大衆の中にいても才能が外に現れることをあらわす言葉「囊中の錐」。
この言葉は有能な人がいれば、必ず頭角をあわらしてくるだろうということを云った中国の古典の一節から来ています。
そこでここでは、「嚢中の錐」という言葉の意味や用いるべき対象、その由来や類義語について見ていきましょう。
目次
「囊中の錐」とは

まずは「囊中の錐」という言葉について、その意味や用いる対象について見ていきましょう。
「囊中の錐」の意味
「囊中の錐」とは、優秀な人は大衆の中にいても、その才能故に自然と目立つという意味の言葉です。
「嚢中」が袋の中のことを指しており、小さな穴を開けるための工具「錐」をその袋に入れている様子を描写しています。
布の袋に刃先の鋭い錐を入れて持ち歩いていたら、勝手に袋から錐が頭をのぞかせてしまします。
それと同じ様に、才能がある人が大衆の中や凡人たちと一緒にいても一歩抜きん出た存在として頭角をあらわすだろうことから来た言葉となっています。
目立つ人ではなく、優秀な人に対して用いる
「嚢中の錐」は、大勢の中にいて目立つ人を指す言葉ではありません。
声が大きい人などは確かに注目を集めやすいかもしれませんが、それは才能や努力によるものではありません。
「囊中の錐」で対象となるのは、優れた人や才能に溢れた人となります。
そのため、派手な人や悪目立ちする人についてもその対象とはなりえません。
「囊中の錐」の由来

では「囊中の錐」という言葉はどのようにして生まれたのか、その由来について見ていきましょう。
中国の歴史書「史記」-平原君伝の一節から
「嚢中の錐」は、古代中国でまとめられた歴史書の「史記」の平原君伝にある一節を出典としています。
その中に「夫賢士之処世也、譬若錐之処嚢中、其末立見」とあります。
これは、戦国春秋時代にあった国「趙」の公子・平原君と毛遂という人物の会話の一部です。
この時、平原君は自国が攻められようとしていたので「楚」という国に救援を求めに行こうとしていました。
そこで、同行者を募っていた時に名乗りをあげたのが毛遂です。
しかし、平原君は特に毛遂に輝くものを見いだせませんでした。
そこで「賢く才能がある人が世に出るときというのは、嚢の中に錐が入っているようなものでひとりでに世に出てくるものだ」と言いました。
更に続けて「ところが毛遂は自分のもとに3年もいるが、未だに誰かがあなたの才能を褒めたり、凄さを話題に出していることを聞いたことがない。そのため、才能があるとは判断できないので今回の任務には連れていけない」と伝えました。
つまり「嚢中の錐」は優れた人は世に自ずと出てくるということを例えた言葉ということになります。
そして、会話の相手にあなたは才能がないと伝えた際に用いられた言葉でもあります。
ちなみに、毛遂はこの後「今までの自分は嚢の中に入ってもおらず、たった今嚢の中に入れてくれと懇願したのだ。もしもっと前から嚢の中に入っていたら錐の刃先がツンと出ているどころか根本まで嚢から出ていた」と食い下がったことで、平原君に同行を許されたそうです。
別の表現がされることも
「嚢中の錐」は、他の表現をされることもあります。
それは、「錐嚢」や「錐嚢中に処るがごとし」といった表現です。
他にも「嚢中之錐」という四字熟語風に表現されることもあります。
いずれの表現でも「嚢中の錐」と意味は同じとなっています。
「囊中の錐」の類義語

最後に「囊中の錐」の類義語について見ていきましょう。
「囊中の錐」の類義語には「紅は園生に植えても隠れなし」や「藪に剛の者」があげられます。
紅は園生に植えても隠れなし
「紅は園生に植えても隠れなし」とは、優れた者はどこにいても人目に立つということを例えた言葉です。
「紅」はベニバナのことを、「園生」は草木を植える庭園のことを指しています。
庭園の中にベニバナが咲き誇っていたら一際目立つ存在となるでしょう。
それらの様子から生まれた言葉とされています。
藪に剛の者
「藪に剛の者」とは、軽んじられている者の中にも立派な者が交じっているということをあらわしています。
「藪」は草深い藪の中のことを、「剛の者」は優れていて強い人のことです。
草が深いようなところであっても優れた人はいるものだというであるということを言っているわけです。
まとめ
「嚢中の錐」は、優れた人は集団の中にいても自然と目立ってしまうという意味の言葉です。
派手だったり声が大きいので目立つという人を指す表現ではなく、優秀であるがゆえに頭角を現すということをあらわしています。
これは、古代中国・戦国春秋時代にあった趙国の公子・平原君と毛遂という人物のやり取りを出典とした言葉です。




