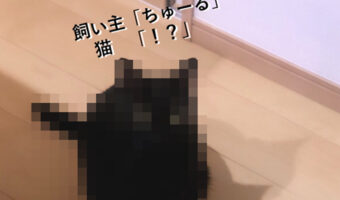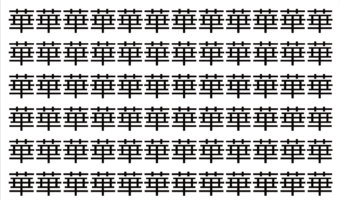一定の基準や方式ですべてを律しようとすることを「杓子定規」と言ったりすることがあります。
この言葉は、ある方法に固執していることを指すこともあります。
では、なぜその様子をあらあわす言葉が「杓子定規」となるのか、ここでは「杓子定規」の意味や由来、その類義語について見ていきましょう。
目次
「杓子定規」とは

まずは「杓子定規」という言葉について見ていきましょう。
「杓子定規」の意味
「杓子定規」とは、一定の基準や形式で、すべてを律してしまおうとすることを意味します。
1つの見方でしか物事や人物を見ることのできないこと、そのため融通が利かなくなってしまうことや頭が固いことを指して用いられることもあります。
「杓子」とはこんな道具
「杓子定規」の「杓子」とは、汁や飯などを盛ったりよそったりする道具です。
当然、「定規」のように直線などを引くための道具ではありません。
「杓子定規」の由来

「杓子定規」はどどのようにして生まれたのか、その成り立ちについて見ていきましょう。
杓子を定規にしようとする行動から
「杓子定規」は、「杓子」を「定規」にしようとしている姿から来ている言葉とされています。
「定規」は古くから真っ直ぐな形状が一般的でしたが、「杓子」というのは柄はもともと曲がっているのが一般的でした。
その曲がっている「杓子」の柄を、無理やり「定規」代わり使おうとする姿から生まれたというのです。
「杓子定規」の類義語
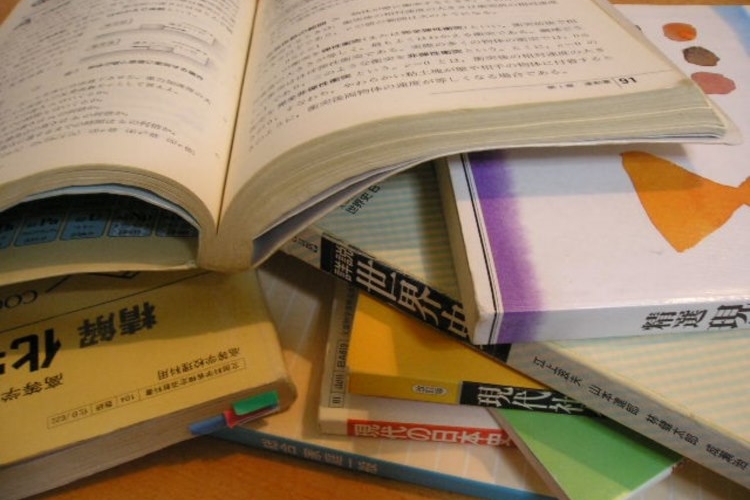
最後に「杓子定規」の類義語について見ていきましょう。
その類義語としては「四角四面」「頑固一徹」「教科書通り」などが挙げられます。
四角四面
「四角四面」とは、極めて真面目であること、生真面目であることを意味します。
逆にそれが行き過ぎて面白みに欠けることを指す言葉でもあります。
思考や態度などが堅苦しい人や頭が固い、融通がきかない人という意味合いで用いられることもあります。
頑固一徹
「頑固一徹」とは、自分の思考や態度を曲げようとしないことや人物です。
非常にかたくなで意地を張っている、そんな自分のことを押し通す人に使用されます。
教科書通り
「教科書通り」とは、物事はこうあるべきという理念に忠実なことを例えた言葉です。
正しいと思った固定概念を貫き通すという意味でも用いられます。
見本通りにしか行動せず、その枠の外から頑なに出ようとしたいという意味合いで用いられることもあります。
まとめ
「杓子定規」は、ある方法や方式に囚われていることをあらわす言葉です。
特定のやり方に固執して、その方法ですべてを律しようとすることに対して使用される他、融通がきかない頭が固い人に対して用いられる言葉でもあります。
褒め言葉としては用いられず、ネガティブな表現となります。