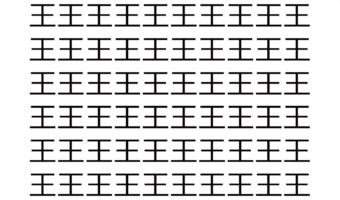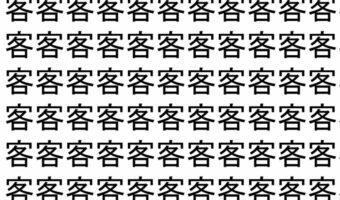愛好家の多いワイン、その度数はどれくらいなのでしょうか。
実はワインのアルコール度数は状況によって変わります。
しかし、厳密にはある条件を満たしたものでないとワインとは呼べません。
今回はそれらワインとアルコール度数の関係について解説します。
ここではワインが持つアルコール度数はもちろん、どのようにしてアルコール度数が決まるのかについても説明します。
目次
ワインのアルコール度数はどのくらい?

まずはワインのアルコール度数がどれくらいなのか見てみましょう。
ワインのアルコール度数の目安
厚生労働省によるとワインのアルコール度数の目安は12%と定められています。
つまり、市販されているワインはこの基準を守っているわけです。
しかし、ワインは種類も無数にあり、この限りではありません。
例えば、ワインの中には12%より高いものも低いものもあります。
そこは厳密に規定されているわけではありません。
他のアルコールはどのくらいのアルコール度数?
ワイン以外にもアルコール飲料はいくつかあります。
例えば、日本にあるお酒の中でもビールや日本酒や焼酎、ウイスキーやブランデーなど多種多様です。
以下、ワイン以外のアルコール飲料が持つアルコール度数の目安となります。
・ビール:5%
・日本酒:15%
・焼酎:35%
・ウイスキー・ブランデー:43%
このようにそれぞれのアルコール飲料によってもアルコール度数は様々となります。
ワインのアルコール度数の決まり方

ではワインのアルコール度数はどのようにして決まるのでしょうか。
ワインのアルコール度数は糖度で決まる
ワインのアルコール度数はブドウの糖度によって決まります。
そもそもワインはブドウ果汁に酵母を加えて作られます。
その際、酵母はブドウの当分を分解してアルコールを生むのです。
そのため、糖度によってアルコール度数が決まるわけです。
特に糖度が高いほどアルコール度数も高くなります。
逆に糖度が低いほどアルコール度数も低くなります。
アルコール度数20度を超えるワインはない?
ワインのアルコール度数は20度を超えるものが存在しません。
実は、酒税法で果実酒はアルコール度数20度未満と定められています。
そのため、アルコール度数20度を超えることはないのです。
厳密にはアルコール度数20%を超えるものも作れますが、それによって作られたお酒はワインとは呼ばれないわけです。
他にもあるワインのアルコール度数を決める要素

他にもワインのアルコール度数を決める要素がいくつかあります。
例えば、産地や品種、収穫時期によって変わることが多いです。
ブドウの産地
ワインのアルコール度数は産地によって決まることがあります。
前述通り、ワインのアルコール度数はブドウの糖度で決まります。
このブドウに含まれる当分は産地の気候や風土によって異なるのが特徴です。
特に温暖で日照時間が長い地域ほど糖度が高くなります。
逆に寒冷で日照時間が短い地域ほど糖度も低くなります。
それらの影響で糖度が上下し、アルコール度数も変わるということです。
ブドウの品種
ワインのアルコール度数は品種によっても変わります。
当然、糖度は使用されるブドウの品種ごとに違います。
そのため、糖度の高い品種はアルコール度数も高くなりやすいです。
逆に糖度が低い品種はアルコール度数も低くなりやすいわけです。
ブドウの収穫時期
ワインのアルコール度数は収穫時期によっても違います。
通常、ワインに使用されるブドウは決められた期間内で収穫します。
しかし、あえて1週間ほど遅らせてから収穫することもあるのです。
それら遅摘みと呼ばれる手法で収穫したものは糖分が凝縮されます。
当然、糖分が高いのでアルコール度数も高くなるわけです。
逆に早摘みしたものは糖分が低いのでアルコール度数も低くなります。
まとめ
ワインのアルコール度数は通常、12%と定められています。
厳密には20%未満のものであれば果実酒として認められます。
それらワインのアルコール度数はブドウの糖度によって変わるのが特徴です。
その他、ブドウの産地や品種、収穫時期によっても変わります。
それがワインのアルコール度数を左右する要素となるので、ぜひ覚えておきましょう。