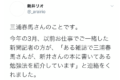毎年11月1日は「紅茶の日」とされています。
ただ、なぜ11月1日が「紅茶の日」とされているか。
そこにはある歴史上の人物が関係しているのだとか。
今回はそんな「紅茶の日」について解説します。
目次
「紅茶の日」とは

まずは「紅茶の日」とはどのような日なのか見ていきましょう。
「紅茶の日」が制定されたのは・・・
「紅茶の日」が制定されたのは1983年のことです。
日本紅茶協会が11月1日を「紅茶の日」と定めたとされます。
では、なぜ11月1日が「紅茶の日」となったのでしょうか。
11月1日となった理由
11月1日が「紅茶の日」となった背景にはある歴史上の人物が関係しているそうです。
その昔、海難事故に遭ってロシアに漂着した日本人がいました。
その日本人に含まれていたのが伊勢の国(三重県)の船主だった大黒屋光太夫という人物です。
当時、大黒屋光太夫は日本にすぐ帰国できると思っていました。
ただ、帰国の許可を得るまでに相当な時間がかかってしまいます。
結果、ロシアに10年間滞在せざるを得なかったのだとか。
そんな中、帰国を切望する生活の中で大黒屋光太夫はロシアの上流階級に普及しつつあった“お茶会”に招かれます。
1791年11月には女帝エカテリーナ2世との接見も許されるという幸運にも恵まれ、実際に彼女のお茶会にも招かれたそうです。
そこで大黒屋光太夫は日本人として初めて外国の正式なお茶会で紅茶を飲んだと言われています。
その出来事から11月1日が「紅茶の日」として定められたのだとか。
「大黒屋光太夫」は何者なの・・・

ここからは大黒屋光太夫という人物について見てみましょう。
数奇な運命を辿った商人「大黒屋光太夫」
大黒屋光太夫は江戸時代後期に活躍した商人です。
特に伊勢国奄芸郡白子の港を拠点とした回船の船頭でもあったとされています。
1782年、江戸へ向かっていた大黒屋光太夫は嵐に巻き込まれ漂流してしまいます。
その後、アリューシャン列島のアムチトカ島に漂着したとか。
そこでロシアのサンクトペテルブルクで女帝と面会して帰国を懇願、漂流から約10年後の1792年に帰国したとされています。
まさに数奇な運命を辿った商人と言えるでしょう。
帰国後の活躍は・・・
大黒屋光太夫がロシアに漂着した当時、老中を務めていた松平定信は彼を利用してロシアとの交渉を目論んでいたそうです。
しかし、その画策が失敗に終わり失脚してしまいます。
対して、大黒屋光太夫は帰国後江戸で屋敷を与えられたとか。
その後は異国見聞者として桂川甫周や大槻玄沢ら蘭学者と交流し、蘭学の発展に寄与した人物として記録されています。
なお、大黒屋光太夫に関しては甫周による聞き取り『北槎聞略』が資料として残されています。
波乱に満ちたその人生は小説や映画などでも描かれているほどなので、気になる方は作品も見てみてください。
「コーヒーの日」は10月1日!

「紅茶の日」に対して「コーヒーの日」というのもあります。
ここからは「コーヒーの日」についてもまとめます。
「コーヒーの日」が制定されたのは・・・
「コーヒーの日」が制定されたのは1983年のことです。
全日本コーヒー協会が10月1日を「コーヒーの日」と定めたとされています。
10月1日が「コーヒーの日」となった理由
「コーヒーの日」は全日本コーヒー協会が独自に制定した記念日です。
そのため、世界各国にある「コーヒーの日」とは別物です。
ただ、国際協定では毎年コーヒーの新年度開始を10月としているのだとか。
この慣習から10月1日を「コーヒーの日」とするようになったとされています。
この慣習はシェア40%を誇る一大生産地のブラジルにあります。
ブラジルではコーヒーの収穫・出荷サイクルを10月1日スタートとしているのだとか。
ここから「コーヒーの日」が定められたわけです。
また、日本では秋冬期になるとコーヒーの需要も高まります。
その結果、10月はコーヒーの供給も増えるとされています。
その点も10月1日が「コーヒーの日」になった理由とされているそうな。
まとめ
毎年11月1日は「紅茶の日」となります。
この日は大黒屋光太夫が初めてお茶会で紅茶を飲んだ日です。
そのため、みなさんも初心に帰って初々しい気持ちで紅茶を飲んでみてはいかがでしょうか。