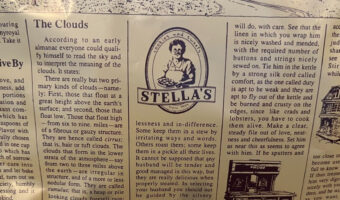何かに極端に熱中してどうしようもなくなることをあらわす「病膏肓に入る」。
この言葉は、病気が重くなって治療の見通しが立たなくなることを指す言葉の意味が転じたものです。
ここでは、この「病膏肓に入る」という言葉について、その意味や由来、類義語について見ていきましょう。
目次
「病膏肓に入る」とは

まずは「病膏肓に入る」がどのような言葉なのか、その意味の変節を見てみましょう。
「病膏肓に入る」の元々の意味
「病膏肓に入る」とは、病気が重くなって治る見込みがなくなることをあらわす言葉として生まれました。
すでに病を患っている人が、さらに重い症状を抱える表現でした。
また、不治の病にかかることをあらわす言葉としても用いられました。
転じて使われるようになった「病膏肓に入る」の意味
「病膏肓に入る」は、病気が悪化して治療不可能となることを指す表現でした。
そこから転じて、何かに極端に熱中するあまり手のつけられないほどになることの例えとして使用されます。
我を忘れるほど夢中になっていることを表現する際に使用されます。
「病膏肓に入る」の由来

では、「病膏肓に入る」はどのようにして成立下言葉なのでしょうか?
「膏」と「肓」とはどこのこと?
「病膏肓に入る」の、「膏」は心臓の下で「肓」は横隔膜の上をあらわしており、「膏肓」で体の奥深くを意味することもあるそうです。
中国の古典「春秋左氏伝」にある逸話が由来
「病膏肓に入る」は、古代中国において孔子が編纂した歴史書「春秋」の注釈書にあたる「春秋左氏伝」を出典とする言葉となります。
紀元前6世紀、春秋時代の中国に「晋」という国がありました。
この晋の君主、景公が病に伏していたときのことです。
病気が重くなったために隣国「秦」から名医といわれていた「緩」という医者を呼ぶことが決まりました。
すると、景公の夢に病気が2人の子供の姿となって出てきました。
夢の中で子供の1人が「名医が来るそうだから隠れてしまおう」と提案しました。
その意見に賛同したもう1人が「肓の上、膏の下に潜り入れば名医だろうと手は出せまい」と答えるのを聞きました。
そして、実際に医者が診てみると「肓膏に病気が及んでいるため、もうどうにもできない」状況にあることが分かりました。
この景公の話から、「病膏肓に入る」という言葉は生まれたとされています。
「病膏肓に入る」の類義語

最後に「病膏肓に入る」の類義語を見ていきましょう。
類義語としては、「血眼になる」「無我夢中」などがあげられます。
血眼になる
「血眼になる」とは、目を血走らせている様子から来た言葉です。
冷静さを失いながらも行動をするという意味で用いられます。
その姿から、必死になり他のすべてを忘れて一つの物事に集中している様子をあらわす言葉としても用いられます。
無我夢中
「無我夢中」とは、心を奪われて無意識にただひたすら何かをする様子のことです。
文字通り、我を忘れて夢中になっていることの表現とされます。
他の物事が疎かになるほど熱中している様子を表す際に用いられます。
まとめ
「病膏肓に入る」は。病気が悪化し手に負えない状態となることから来た言葉です。
それが転じて、何か一つのことに対して極端に熱中している様子をあらわす言葉として用いられるようになりました。